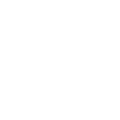NEWS
BACKアクエリアス・アルゴリズム第1話【一部無料公開】
2020.02.07
1
ススキやアザミといった秋の草花が、朝の穏やかな風に揺れている。まだ低い位置にある太陽の陽射しを受けて、人造湖の湖面にはさざ波がきらめいていた。平和──そう呼んで差し支えない光景。ここがかつて〈遊星爆弾〉と呼ばれた異星の兵器が作った禍々しいクレーターだったことを伺わせるものは何も無い。
西暦2215年。33歳の古代進は、妻とひとり娘、愛する家族とともにこの湖の湖畔に立つ瀟洒な家に暮らしていた。
「美雪、ごはんできたぞー」
二階のキッチンでは、エプロン姿の古代がチーズ入りのオムレツを器用にひっくり返している。はあいと明らかに眠そうな返事が三階から聞こえた。
古代と雪の一人娘、十一歳になったばかりの美雪がパジャマ姿であくびをしながら降りてきた。黒く健康な髪の毛が、寝ぐせでぴょこりと立っている。
「おはよう、お父さん。お母さんは?」
「もう出たよ。お前、最近夜遅くまで何をしてるんだ?」
「別に?」
「おはよう美雪。今朝の一杯は少々濃いめ。これ飲んでがんばるパピ!」
一月前からこの家に来ている四人目の家族。小型万能ロボット〈パピライザー〉が、カフェオレをカップに注いで美雪に手渡した。
「わかってるね、パピライザー。大好きだよ」
かつての名機〈アナライザー〉によく似た頭部に美雪がちゅっとキスをする。
パステルカラーの準人型ロボットは、嬉しさのあまり下半身を支える高密度発砲素材のスポンジタイヤを器用に回転させて跳びはねた。「動物でもロボットでも、お前はほんと仲良くなるのが得意だな」
オムレツとトーストを並べながら古代が笑ってそういうと
「へへへ、愛情ですよ」
と美雪はうそぶきトーストにかじりついた。じつはここ最近、美雪はパピライザーのカスタマイズにはまっている。連日の寝不足と引き換えに、ふたりの「相棒度」が劇的に高まっていることは両親にはまだ気づかれてはいないはずだ。
美雪の美しい母──旧姓は森という──古代雪はすでに出勤していた。雪は今では軍の上級幹部となって多忙な日々を送っている。
一方、父親である古代進は三年前に予備役になり、軍を半ば退いていた。食事や掃除、ゴミ出しなど、家庭内の仕事を全面的に請け負っている。英雄として名を馳せたかつての古代からは考えられないと言う人々もいるが、美雪はそんな父がきらいではない。
「お父さん、あたし今日は昼には帰ってくるから」
「わかってるよ。ボートは整備済だ」美雪はオムレツとトースト二枚を食べ終えると、歯磨きをして、すばやく身支度を整えていく。
「操縦させてくれるんだよね?」
「ああ、約束だからね。さあ、そろそろ時間だぞ」
「はい、準備完了!行ってきまーす!」
パピライザーが美雪をスクールバス乗り場まで送っていくのを見届けて、古代は皿洗いを始めた。
地球防衛軍艦隊司令部。そのブリーフィングルームでは新たに建造された艦隊旗艦〈ブルーノア〉の運用関連の定例会議が行われている。男性の姿が目立つ室内のテーブル中央には、白い制服姿で発言する古代雪の姿があった。
艦長職を目指している雪の鋭い質問は担当者をたじたじとさせ、雪が提案するプランは上層部の面々にほうと感嘆の吐息を漏らさせた。
二時間後、与えられているオフィスに戻った雪がレポートをまとめていると、ドアがノックされた。
「どうぞ」
ドアが開き、長身の男が顔をのぞかせた。意外な、しかし懐かしい人物だ。
「雪、久しぶりだな」
「真田さん!」
元ヤマトクルーの真田志郎は、今や科学局の副長官にまで出世していた。
「まさかここにいらっしゃるなんて」
「ああ、直接話したいことがあってな。君の方は順風満帆だな。古代雪の優秀さはこちらにまで聞こえているよ」
堅物なのに暖かい。そんな真田の変わらない物腰に雪も微笑まざるを得ない。
「オーバーですね。真田さん、お茶でもいかがですか」
司令部最上階のカフェからは、次々に離発着する軍艦を遠望できた。
「美雪ちゃんは大きくなっただろうな」
「ええ、元気ですよ。もう元気過ぎるくらい」
「古代の様子はどうだい」
しばらく会っていない弟を気遣うようなニュアンスで真田は聞いてくる。
「……落ち着いてはいます。時々悪い夢を見ているようですが」
「ベルライナか」
「おそらく」
「警護艦隊の指揮官だった古代が、あのとき任務の範囲を超えて他国の戦闘に介入したのは確かだ。だが古代のあの決断がなければ悲劇はもっと大きくなっていた」
真田の言葉に、雪は無言でうなずく。
「しかし結局軍は古代を処罰して、予備役に編入してしまった。藤堂長官のいた頃とは軍もすっかり変わってしまった」
「私は夫の決断を支持します。誰に恥じることもない、立派な行いです」
「無論だ。それは多くの人がわかっている」
真田のその言葉は、雪を励ます力に満ちていた。だが、周囲の想いは夫には届かない。夫は、古代進は今も自らを責め、悪夢にうなされている。
「あの人は優しすぎるんです。どれほど多くの人を救っても、救えなかった命の重さを忘れることができない」
そう言ってしばらく、雪も真田も黙っていた。窓の外では断続的に軍用機が飛び立っていく。
ここまで赤裸々な話をすることになるなんて、雪は思ってもいなかった。だが真田を前にしたとき、彼女の中で張りつめていたものが不意に緩ゆるんでしまったのだ。
ヤマトに命を預けたかつてのクルーたちは皆、家族と呼ぶほかない不思議な結束を保ち続けている。ヤマトが沈んでから十二年も経つのに。
そのことの不思議さをぼんやりと考えていた雪に、真田は声を低くして話を切り出した。
「実は、古代ときみに聞いてもらいたい話があって来た」「私たちふたりに」真田はうなずき、驚くべき言葉を静かに口にした。「ヤマトが見つかった」