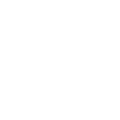NEWS
BACKアクエリアス・アルゴリズム第1話【一部無料公開】
2020.02.07
3
真田、北野、太助という気のおけない来客たちを見送り、美雪が自室で眠りに落ちたことを確認すると、古代夫妻は湖の見える二階のテラスに出た。
夜空には、月とアクエリアスがそろって浮かんでいる。
「今日はどちらも満月か」
「ええ。湖に舟を出している人も多いみたい」
目の前の湖は、かつてガミラスの遊星爆弾によって穿かれたクレーターだった。それがいつしか湖となり、今では〈創星湖(そうせいこ)〉と呼ばれている。人々が希望を込めてそう名付けたのだ。
「雪の艦長昇進試験、もうすぐだな」
「そうね……」
テラスでワインを傾けながら二人は天空を見つめていた。
いま銀河系でテロ活動を続けているディンギル人は、十二年前ディンギル帝国として地球と死闘を繰り広げた。終局の時、大神官大総統ルガールは本拠地たる都市衛星ウルクを自爆させてヤマトを沈めようとしたが失敗。ルガールたちを乗せたディンギル最後の艦隊も、駆け付けたデスラー総統の手で沈められた。ディンギル人たちが今ガルマン・ガミラス宙域で破壊工作を繰り返すのは故なきことではなかった。
もちろん地球側にも大きな打撃はあった。ヤマトも傷つき、ウルクでの激闘のなか、古代の親友だった島大介は戦死した。
今夜は風もなく、湖面はどこまでも静かだった。
亡き友に古代は心のなかで語りかけた。
──島、あれが人類最後の戦争だ。あれから十二年、戦いは起きていない。この平和が続くように微力を尽くすよ。
歴史上〈アクエリアス事変〉と呼ばれる、ディンギル帝国との戦争と、彼らが操る水の惑星アクエリアスによる地球水没の危機。二つの事態が絡まり合いながら進行した終局の時、乗員すべてが退艦したヤマトの第一艦橋で、古代と雪は沖田十三艦長と向かい合っていた。
──古代、雪、いい子を産むんだぞ。
沖田艦長は、そう言って二人を抱きしめた。それが、彼が二人にかけた最後の言葉となった。
「次の艦長の命日は十三回忌になるんだな」
古代はつぶやく。
雪はうなずき、古代の肩に頭をあずけた。月に照らされた雪の髪が金色に輝き、夜風にさらさらと靡(なび)いた。
同刻──アクエリアスの氷床(ひょうしょう)からは、吹きすさぶ嵐の向こう側に、地球が月とほぼ同じ大きさで見えていた。
気密服を着こんだ兵士たちが、機械の馬にまたがり険しい氷の丘を駆け上っていく。
ロボットホース──それはアクエリアス事変において、都市衛星ウルクで展開した熾烈な白兵戦で、ヤマトに挑んだディンギル兵たちの乗騎だった。それとまったく同じものが十数騎、整然と連なり、氷を蹴って走り去った。
その光景を凍結した海面から、じっと見つめる目があった。
潜望鏡はディンギル兵の行動を確認し終え、氷を溶かしながら海面下に消えて行く。
氷に開いた穴はすみやかに閉じ、瞬時に凍結してしまった。アクエリアスの氷は、ただの水から構成されているのではない。未知の物理構造を有しているのだ。
十メートル、二十メートルと潜望鏡は下がり、氷床の下層にできた空洞内に身を潜めている〈潜水船型の艦〉に格納された。氷床から射し込むわずかな地球光の反射ではその船の詳細は把握できない。突起の少ないシンプルなシルエット。無彩色の塗装を施された船体には所属を示すエンブレムも見当たらない。舷側(げんそく)に〈氷華〉という船名を刻んだその船は氷の底の闇の中で、沈黙したままたたずんでいた。
真田に依頼されてから十週間、いよいよ明日の早朝はアクエリアスに出発するという夜になってもまだ、古代と美雪はリビングで押し問答をしていた。もう何度も同じ話を繰り返している。
「あたしも行きたい行きたい!」
「美雪、説明しただろ。二人で古い戦友を訪ねてくるだけだ。一週間で帰るから」
「えー」
両親の微妙な説明に、美雪は露骨に不平不満を表明した。美雪はパピライザーを使った盗聴で、両親がアクエリアスに行くことを知っているのだ。
「佐渡先生のフィールドパーク、久しぶりだろ?」
「それはそれで魅力的ではあるんだけど」と美雪は複雑な表情を見せた。
ヤマトの艦医だった佐渡酒造は退官後、野生動物が共生できる〈佐渡フィールドパーク〉を設立し、今はそこの園長に収まっている。幼いころからここに通い詰めた美雪が動物好きになるのは当然だろう。だが、今はフィールドパークより、もっと行きたい場所がある。
ソファで跳ねながら「行きたい!行きたい!」とごねる美雪にたじたじの古代。娘の説得は夫には荷が重そうだ。
「しょうがないわね」見かねて雪は、助け舟を出した。
「パピライザー、美雪のボディガードお願いね」
雪の言葉に、パピライザーはピピっと光って返事をした。佐渡医師のところには、自分の原型である〈アナライザー〉がいる。アナライザーとはAI上の親子関係を結んでいる。パピライザーのほうが新型だから子供ということに二機で決めたのだった。
「久しぶりにパパに会えるの、うれしいでパピ!」
「あー!裏切り者!」
「そうと決まったら早く寝なさい。ちゃんと明日のお昼のバスに乗るのよ」
翌朝早く、科学局の制服を着た古代と雪が、薄もやのかかった湖畔に佇んでいる。やがて、真田が手配した迎えの船が定刻通り空の向こうに見えてきた。
船体下部からガスを噴射しながら、白い船体に赤い船底の船は創星湖の湖畔に着陸した。
「古い機体でも脚は早いと真田さんから聞いていたが、まさか、あれ…とはな……」
古代と雪は顔を見合わせる。
それはかつてデザリアム軍に占拠された地球から脱出する際に威力を発揮した機体だった。──大統領専用高速連絡艇。あれが現存していたとは、二人は思ってもみなかったのだ。
しかしすぐには歩み寄る気にならない。
二人にとって、この船にはあまりに生々しい思い出がありすぎた。
機体中央部のハッチが開きタラップが下ろされたが、古代はあの日のことを思い出して船体を見上げ、しばし動けないでいた。暗黒星団帝国の急襲を受けて、古代たちはこの連絡艇で脱出を試みたのだった。あのとき二人の手が離れ、一時的だったとはいえ、古代と雪は離れ離れになってしまった。互いに「きっと生きている!」と信じていたが、不安に押しつぶされそうな日々だった。掴んでいた手を離してしまったあの瞬間の絶望が、いま古代の中で急速に蘇っているのだ。
「古代君」
それはとても懐かしい呼ばれ方だった。
いつのまにかタラップを上がっていた雪が振り返って、古代に手を差し出している。
ふたりの位置はあのときとは真逆だったが、古代は雪の手をしっかりと握ってタラップを上っていった。その光景を、玄関わきの植え込みに隠れてじっと見つめる目があった。
「敵を欺くにはまず味方から。ロボット三原則すれすれパピ」
リュックに帽子を装備した美雪が双眼鏡を下ろした。
「なーに、あのスチームアイロンみたいな船」
「ダサイかもです。行きましょうパピ!」
美雪とパピライザーは背の高い草むらに身を隠しながら船に近づき、収納され始めた昇降タラップに向かって駆け出した。
「ボクに捕まってパピ!」
「お願い!」
美雪をおんぶしたパピライザーは、両腕の伸縮機能を全開にし、タラップの下端を掴んだ。タラップはそのまま格納されていく。
ふたつの影が艇内に潜り込んだ直後、連絡艇は浮上を始めた。湖を眼下に見ながら転進、明け始めた空に浮かぶアクエリアスを目指し、ツートンの機体は猛スピードで飛び去っていった。
「地表アンテナが飛翔体を感知しました。アクエリアスに向かって来るようです」
灯りを落としたさほど広くもない空間に、淡々とした報告の声が響いた。深海作業艇の操縦席をやや大型化したようなレイアウト。その室内に薄汚れた服を思い思いに着こなした汗くさい四人の男たちがいる。誰もがそれぞれの席で無言で作業を行っていた。
「氷華、千メートル潜航」
中央の席に座る大男が、腕を組み瞑目したまま指示を出した。
クルーたちはそれに答え必要な手順を連携していく。やがて室内に振動が伝わり「潜航スタート」の報告がもたらされ大男は閉じていた眼を開いた。その双眸からは、なんの感情も読み取れなかった。