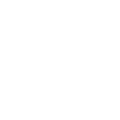NEWS
BACKアクエリアス・アルゴリズム第1話【一部無料公開】
2020.02.07
2
午後の陽射しが、凪いだ湖面に青空と雲を映している。
湖に突き出した木造の桟橋に座り込んだパピライザーは、湖面に釣り糸を垂れたままじっと真っ赤な浮きの動きを見つめていた。釣りはパピライザーのAIにとってかけがえのない大切なひと時であり、雰囲気を高めるために麦わら帽子までかぶっているのだ。
風がススキの野をわたっていく。
びくんと大きな手ごたえがあった。
「パピ!」
パピライザーはタイミングを計って一気に竿を引いた。
美しいヤマメの大物が釣り上がり、さらにピピピと感動していると、小型エアカーが湖面に飛沫を立てながら、こちらに向かってくるのが見えた。
「ピ?」
制服を着た二人の青年がエアカーから颯爽と降り立った。
「やあ、パピライザーだろ?」「古代さんの家に連れて行ってくれ!」
パピライザーはたちまち彼らの顔を認証した。身元は確実。怪しい人物ではない。
パピライザーは釣果をクーラーボックスに入れて移動を開始した。
かなりの高速移動だったが、鍛えられた肉体の二人は余裕で後を追いかけていった。
「北野!太助!」
古代はドアを開けるなり目を丸くしてしまった。
玄関前では北野哲と徳川太助が制服姿で敬礼していた。
「お客さんパピ!」
不意を突かれて反応できない古代のわきをすり抜けて、パピライザーは釣りあげた魚をぶら下げてキッチンへ走る。
古代は懐かしい戦友たちをリビングに通した。
一人は北野哲。宇宙戦士訓練学校を首席で卒業した秀才だ。
もう一人は徳川太助。父親の彦左衛門と同じくヤマトの機関部員だった。
二人ともあの時代、古代や雪と共にヤマトに乗り、ヤマトと共に戦った紛れもない戦友だ。
二人は今も、退官することなく地球防衛の任についている。十五ヶ月の外洋警護任務を終えて今朝地球へ帰還し、その足でここへ来たのだと聞かされ、古代は言葉を失った。
報告任務や家族との再会の前に、我が家を訪ねてくれたことはありがたいが、申し訳なさは否めない。太助には元ヤマト乗員の妻と二人の子供もいる。それに二人とも激務で疲れているのは確実だ。
「来てくれたのはもちろんうれしいが、何かあったのか」
「ええ、古代さんに直接お話ししたいことがあって」
北野は、太助とうなずき合ってから語り始めた。
「銀河中心部の気象は相変わらずひどい有様です」
「……だろうな。〈銀河交差〉の影響が完全に落ち着くのは、俺たちの何世代も後の事だろう」
そう答えた古代の脳裏に、十二年前の大気象変動の光景がまざまざと蘇った。
〈銀河交差〉。それは西暦2203年に突如発生した宇宙規模の災害だった。地球が属する天の川銀河に対して、異次元から現れた別の銀河が衝突・交錯するという異常事態は、天の川銀河の中心宙域に壊滅的な被害をもたらした。多くの星系が徹底的に破壊され、その被害は丸十二年を経た今もまったく恢復(かいふく)していない。
これによって、ガルマン・ガミラスとボラー連邦という銀河の二大国は、存亡の危機に立たされた。国力を衰退させた両陣営は、長年の領土間戦争を棚上げし、休戦協定を結ぶことになった。
銀河交差から二年後の西暦2205年。ガルマン・ガミラス帝国は、気象大変動の収まらない銀河中心部から、星間国家丸ごとの一時的避難を決定することになる。かつての支配圏だったマゼラン星雲への民族大疎開──〈マゼランエクソダス〉だ。
デスラー総統の指揮のもと断行されたこの大事業は、その当初から地球にも大きな影響を与えることになった。地球も全面的に協力することになったからだ。
ガルマン・ガミラスの人民には、銀河系中心部に残ることを選択した者や、残らざるをえなかった者が少なからずいた。こうした人々の安全保障を、ガルマン・ガミラス政府は友好国地球に要請した。地球はこれを受け入れ、移民支援と残留者保護を国家政策として打ち出したのだった。
「すまないな。本来は俺も、お前たちと一緒に任務にあたるべきなんだが」
「俺たちも早く古代さんが現場に戻れるように動いています」
あれから十年……保護政策は一定の成果を挙げていた。銀河内に存在していた未知の惑星国家と邂逅、友好を深める例もあった。新たに国交が開かれた〈アマール〉などはそうした星のひとつだ。
しかし明るい話より、暗く厳しい出来事の方が遥かに多かった。
古代が心に深い傷を負うことになった〈惑星ベルライナの悲劇〉も、この保護政策を進めていくなかで生じた。ガルマン系住民とボラー系住民が、両大国のくびきが突然失われた結果、惑星全体で内戦を始めてしまったのだ。地球の対応は遅きに失した。
内戦に〝介入〟した責任を取って予備役に退くことを受け入れた古代だったが、似たような事件はその後もあちこちで繰り返されていると聞く。
「銀河交差を境に、宇宙の様相はすっかり変わったな」
古代はつぶやくように言った。
星間国家同士の大規模戦争こそ起きなかったが、銀河系全体はテロと民族紛争が頻発する混乱の時代に突入した。
なかでも二年前、〈ディンギル人〉によって引き起こされた地球の植民惑星〈ボギーニャ〉の大虐殺はあまりにも生々しい悲劇として誰の心にも刻み付けられていた。
「古代さんに話したかったのはそのことなんです。ここ数ヶ月、元々ガルマン・ガミラスの政府機能があった星系を中心に、テロが急増しているんです」
北野の言葉を太助が継ぐ。
「無人の偵察衛星が爆破されるといった事件ばかりなんですが、地球防衛軍としては看過できないということで、俺たちも本部に報告が終わり次第、また派遣されることになると思います」
胸の奥に広がり始めた暗い予感。古代はしばしの沈黙の後、その名を口にした。
「ディンギルが関係しているのか?」
「どうでしょう。確かにディンギルは、地球とガミラス双方に恨みがありますが……」
北野がためらいがちに答え、太助がうーんと考え込んでいると、いきなりドアが開いて、
「あー!太助おじちゃん、北野のお兄ちゃん!お帰りなさい!」
帰宅した美雪が屈託なく座に飛び込んできて、深刻な空気は一気に晴れた。
「美雪ちゃん、なんでこいつがお兄ちゃんで、俺がおじちゃんなんだよ!」
妻のすすめで始めた肉体改造の成果で、ぽっこりしたお腹を消滅させつつある太助が真顔で抗議し、一同のあいだにどっと笑いが起きる。
「今日はお客さん、いっぱいだね」
「ん?お客さんって僕たちのことかい?」と北野。
「違うよ!」
そう答えた美雪の後ろから、聞き慣れた声が響く。
「賑やかにしてるな」
雪と一緒にリビングに突然現れた人物に、全員が声を上げた。
「真田さん!」
真田は古代とうなずきあってから、その奥の北野と太助に声をかけた。
「古代と雪に話した後で、お前たちにも説明するつもりだったが、その手間が省けた。と言うよりお前たち、勘が良すぎるぞ」
にやりとした真田の視線を受け、北野は頭に手を回し、太助はへへへと笑った。
古代と雪は無言のまま視線を交わした。来客たちが今日重なったのはどうやら偶然ではなさそうだ。
「大人の話になりそうだね」
美雪はパピライザーに耳打ちした。
「その可能性は大ですパピ」
「仕方ない。あたしたちは三階に行こう」
「すまないな美雪。ボートは明日だ」
「わかってるって。お父さんの顔見たら、怒る気もなくなった。でも、明日は絶対だからね!」
「明日は絶対だ。でもお父さん、どんな顔してる?」
美雪はうーんとうなってから、「海の男の顔、かな?」
娘の口からそう言われ、古代は微笑んで美雪の頭をやさしく撫でた。
古代夫妻、真田、北野と太助──五人はテラスに出て、テーブルを囲んだ。近くに人家はなく、誰かに聞かれる心配はない。
「まずはこれを見てくれ」
真田が上着の内ポケットから黒いカードを取り出した。小型の投影機だ。真田が触れると、一抱えもある大きさの球状のホログラムが空間投影された。
「アクエリアス……」
古代の呟きに、真田がうなずいた。
アクエリアス氷塊は十二年前の戦いの最後に生まれた、地球の新しい衛星だ。今は月よりも少しだけ近い衛星軌道を巡っている。直径は約千キロメートル。月の三分の一以下だが、地上からは月とほぼ同じ大きさに見える。
人々はアクエリアス氷球の中心に灯った赤い光を、炎のようだとも血のようだとも語っている。その光はより巨大なアクエリアス本体との共通点でもあった。
真田を含めて、五人全員がしばし黙り込んだ。誰もがホログラムのアクエリアス氷塊に、切なさのにじむ眼差しを投げかけている。
あの海に、あのアクエリアスに、あの氷球のなかに、青春のすべてをかけた艦が沈んでいるのだ。
かつて世界を救ったあの偉大な艦のことを忘れ去っている人々も多い。しかしこの場にいる五人は全員、ヤマトのことを片時も忘れたことはない。
ヤマトは地球を幾度となく救い、十二年前、西暦2203年の戦いの果て、巨大な水の惑星〈アクエリアス〉による地球の水没を防ぐために自爆した。アクエリアスから地球へ降り注ごうとする天文学的な質量の水柱を、その身を爆発させることで断ち切ったのだ。ヤマトによって分断されたアクエリアスの巨大な水柱は、地球近傍(きんぼう)に弾け飛び、数カ月間にわたって波打った後、宇宙の真空のなかで冷やされ──時に太陽に熱せられて──ゆっくりと真球に近づきながら凍っていった。そのどこかに自沈したヤマトの亡骸を取り込んだまま。
凍りついた球体は、太陽系から飛び去った本体と同じく〈アクエリアス〉と呼ばれるようになり、今は月と共に、地球のまわりを巡っている。今のところアクエリアスの自転は速いが、いずれは自転と公転の周期が同期して、月のように常に同じ面を地球に向けるようになると考えられていた。
「地球第二の月となったアクエリアスだが、その近傍宙域が封鎖されていることは誰もが知る通りだ。アクエリアスの氷球全体に量子(りょうし)重力(じゅうりょく)効果が広がっていて、艦艇が近づくことはおろか、撮影することもままならない。ヤマトの沈没ポイントを正確に割り出すことが、長年できなかったのもそのためだ」
真田はそこまで言ってホログラムに触れ、一部を拡大した。北側の氷原と、その地下に光点が表示される。
「先日、このポイントに波動エネルギーの輻射(ふくしゃ)が確認された。表面からおよそ千メートルの位置にある」
「〈波動輻射〉……!ヤマトの波動エンジンがまだ活動してるってことですか?」
「太助、波動エンジンの残骸が長時間波動輻射を放出することはお前もよく知ってるだろ」
北野の冷静な言葉に、太助は浮かしかけた腰を再びソファに沈める。
真田は全員を見てゆっくりと話を続けた。
「詳細はわからん。だがヤマトはこのポイントに沈んでいる。沖田艦長とともに」
真田の話は、他の四人の予測の範囲を遥かに超えて、重いものになりつつあった。
テラスでの大人たちの深刻さをよそに、三階では美雪がパピライザーとゲームに興じて、時折歓声をあげていた。
古代は美雪に聞こえていないことを確認してから、真田に問いかけた。
「俺と雪への話というのは、ここへ行け──そういうことですね」
「そうだ。現在のヤマトの姿をその目で確認してもらいたい」
三階の美雪はパピライザーに刺したイヤホンで大人たちの会話を聞いていた。先ほどの歓声は演技だったのだ。
「アクエリアスに上陸できた船はほとんどないんですよね?」と北野。
「自分の知る限り、ゼロだ」と真田。
パピライザーの各種センサーは高性能だ。イヤホンを通して、階下にいる大人たちの緊張や吐息までがリアルに伝わってくる。
真田の解説が続く。
「アクエリアスによる異常な重力勾配が、周辺宙域にまで乱流を発生させているんだ。平均の流速は秒速八千メートル」
「速っ!」
美雪は思わず声にしてしまって、慌てて口を手でふさいだ。大丈夫、下には聞こえてない。
「北野と徳川に加わってもらいたかった理由がわかるだろう?」
真田に認められた二人のちょっとばかり照れた声を聞きながら、美雪は当然の疑問を声にしてみる。
「パピライザー、そんなところにどうやって行くの?すっごい大きな船でも無理だよね?」
「重力波発生装置を使うと思いますパピ!真田さんは科学局の副長官パピ!」
パピライザーの解説に、美雪はうんうんとうなずいた。
しかし両親は本当にそんなところに行くつもりなのだろうか。
「これって絶対危ないよね!」
「そうパピ」
美雪は部屋の窓から、暮れ始めた空にぼんやりと浮かぶアクエリアス氷球を見つめた。
ここでもうひとつ気になる話があると、真田はさらに声を落として話を続けた。
「匿名の情報があった。アクエリアスで密かに活動している集団がいるらしい」
真田の話はソースの不明確さも含め、今一つ捉えどころが無かったが、彼の表情は真剣そのものだ。様々な状況を勘案して、かなり確度が高いと判断しているのだろう。
「警戒すべき事態だ。匿名の人物は防衛軍関係者としか名乗っていないが、アクエリアスをかなり以前から詳細に調査していたようだ。実のところ、ヤマトの沈没ポイントの特定も、その人物からの情報でようやく可能となった」
「匿名の人物と、謎の集団ですか」
太助は腕を組んで考え込んだ。
「沖田艦長の眠る場所にいま何かが起きているのは間違いない。とはいえ場所が場所だ。正面切って軍を送り込むことは避けたい。だからこその今回のミッションだ」
真田の言葉に、全員がうなずく。
「もしかして、さっき二人が俺に話してくれたことにも繋がるのかもしれません」と古代。
「どういうことだ?」北野と太助が警護任務のさ中で感じた不穏な空気の話に、真田は同意を示した。
「ガルマン・ガミラスとボラー連邦、二つの大国が力を失って、これまで潜んでいた勢力が動き出しているのかもしれない。前線にいる二人は敏感に察したんだろう」
そして、だからこそ、北野と太助はその曖昧な感触を伝えるため、古代を訪ねているのだ。
真田は皆に気取られないよう一人ほくそ笑んだ。自分もまた、古代を──弟のような存在と思いながらも──リーダーと認め、こうして訪問しているのだから。今日俺たちがここに集まったのは必然だろう。
「危険を伴う任務になるが……」真田は、古代を見つめて結論を伝えた。
「ヤマトと沖田艦長の今を、その目で確かめて来てくれ。古代」